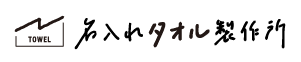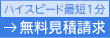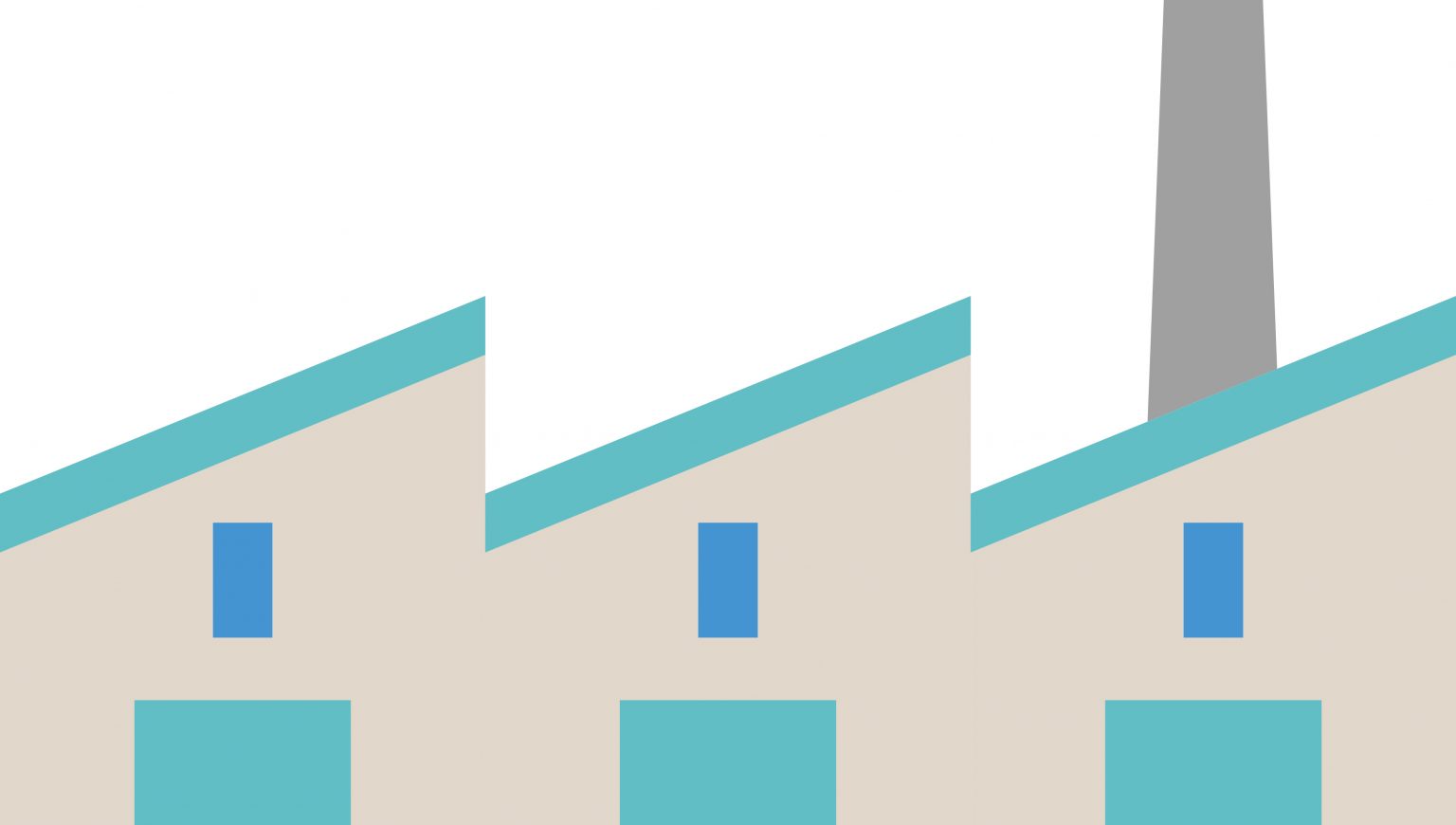タオルの名産地であり、日本のタオルの発祥の地でもある大阪・泉州。
タオルは製造工程でたくさんの水が必要となるため、和泉山脈の豊富な水源がある泉州はとてもタオル作りに適した環境です。
今回は、当店の名入れタオルでお世話になっている泉州タオルの工場へ、製造現場を見学してきましたので、タオルが作られる工程を写真付きでご紹介します!
製織

まずは、糸をタオル生地へ織りあげる場面からスタートです。
写真の機械は「織機(しょっき)」といいます。
織機は糸を引っ張りながら織っていくので、このときに使われる糸には蝋や糊で補強するサイジングという加工がされています。
現場の湿度は70%前後。これくらいの湿度が最も綿に良いと言われています。
季節に左右されないように、加湿器などで徹底管理されています。
ヘムミシンかけ

織りあがった生地の両端をミシン掛けします。
タオル業界ではオーバーミシンと呼んでいます。
この後の製造工程でほつれないようにする補強作業です。
写真の床部分に写ってる白いものはホコリではなく、綿です。
湿度が高いので、どうしても床に貼りついてしまうそうです。
もちろん、後できちんと掃除します。
織りあがりをチェック
高性能の織機を使っているので品質にバラつきはまずないのですが、それでも最後のチェックは人の目で行います。
切れてないか、織りムラはないかなどを確認するために、生地を引っ張るなどして目を凝らしながらチェックします。
生産効率を考えたら省いてもよい作業に思われるかもしれませんが、品質の良さは、機械ではなく、つくり手のこだわりだと考えているのだそうです。
職人のこだわりが伝わってきます。
染色

次は泉州タオルの代名詞である後晒しの工程へ入っていきます。
写真では分かりづらいかもしれませんが、このタオル、生成色です。
生地にまだワックスなどが染み込んでいるため、手触りもゴワゴワしています。
それを次の工程で、白く、そしてふんわりとした触感へとしていきます。
後晒し
糊抜き

まずは、糸に付いていた糊を取り除きます。
ここで作っているタオルの糊は化学系の糊でなく、自然素材の糊。
化学系は薬品を使って落とすのですが、自然素材はお湯で洗えます。
洗った後は、さらに残った糊をバクテリアに食べさせます。

こちらの工場では、アミラーゼを使って糊を食べさせています。
アミラーゼが活発になる温度と湿度を保ち、約18時間かけてじっくり食べてもらいます。
もちろん、化学系の糊を薬品で落とす方が早いのですが、綿が痛むことや使う人の肌への負担を考えて、ずっとこの工程を守り抜いているそうです。
精錬

糊抜きが終われば、次は精錬。
精錬とは、もともと繊維に含まれている油脂、蝋質、ペクチンなどを落とす工程です。
しっかりやらないとタオルの吸水性を引き出せないので、念入りに洗います。
漂白

精錬の後は、漂白です。
漂白とは、精錬で落としきれなかった不純物をさらに取り除き、白さを引き出す加工です。
この工場では、染料や漂白剤を染み込みやすくするために筒内を真空にする工法を用いています。
綿への負担が少ない、自慢の工法だそうです。
染色

カラータオルの場合は、漂白後に染色します。
晒し完了

ここから速やかに乾燥の工程へと移ります。
乾燥の仕方により、シリンダータオルとソフトタオルの2種類のいずれかへ変わっていきます。
乾燥

まずは、乾燥機で水分を65%とばした後、写真に写っている熱したローラーにかけていきます。
綿を痛めないように温度の調整や圧力のかけ方には細心の注意を払ってます。
このローラーをシリンダーが呼ばれているので、できあがったタオルはシリンダータオルというそうです。
表面はアイロンを当てたようなペタッとした仕上がりになります。
ソフトタオルに加工

シリンダータオルに熱風を吹き付けて、毛を立たせると、風合い豊かなソフトタオルになります。
名入れ

名入れは専門の職人へ依頼。心を込めて名前を印刷していきます。
ミシン掛け&裁断

最後はミシン掛けと裁断。
昔は人の手で内職していましたが、今は機械で自動化されています。
完成

ようやくできあがり!
「気持ちよく使ってもらうんやで」と、わが子を送り出すような気持ちで出荷作業をされていました。
ここに至るまでに、多くの泉州の職人の方々が「良いタオルつくりたい!」という想いを込めて作業をしていらっしいました。
最後に
いかがでしたか?
普段何気なく使っているタオルは、 こんなにたくさんの工程を経て作られていたのです。
職人さんのたくさんのこだわりが詰まっていたということが、この記事を読んだ方に少しでも伝わればうれしいです。
さて、名入れタオル製作所で取り扱っている国産名入れタオルは、今回ご紹介した泉州タオルです。
3点までなら無料サンプルもご用意しておりますので、まずは触り心地だけでも体感してください。